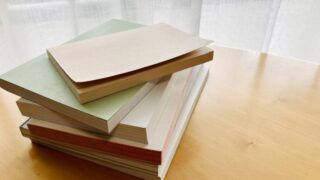 書籍+移住への視点
書籍+移住への視点 「なつかしい時間」(長田 弘著、岩波新書、2013年)
長田宏著『懐かしい時間』の書評。詩人が語る「風景」の重要性と、現代社会が失いつつあるものについて考察します。筆者はこの書を通じて、長崎への移住と不動産事業開始への思い、そして合気道の稽古がもたらす「楽しい風景」を重ね合わせ、地域での新たな価値創造への意欲を語ります。
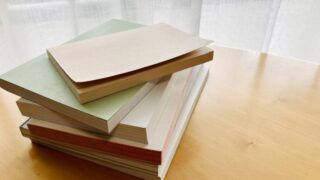 書籍+移住への視点
書籍+移住への視点  風景+叙景・雑感
風景+叙景・雑感  風景+叙景・雑感
風景+叙景・雑感 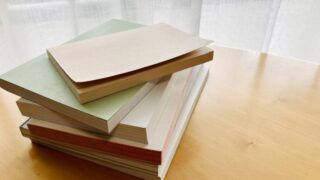 書籍+移住への視点
書籍+移住への視点  データ+移住への物語
データ+移住への物語  データ+移住への物語
データ+移住への物語 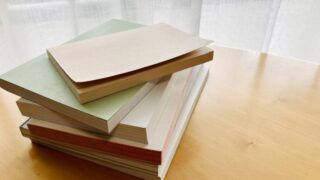 書籍+移住への視点
書籍+移住への視点 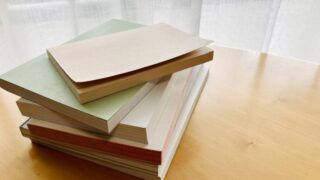 書籍+移住への視点
書籍+移住への視点  データ+移住への物語
データ+移住への物語 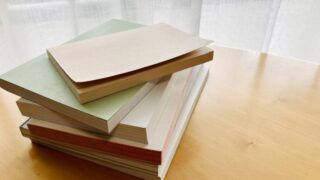 書籍+移住への視点
書籍+移住への視点